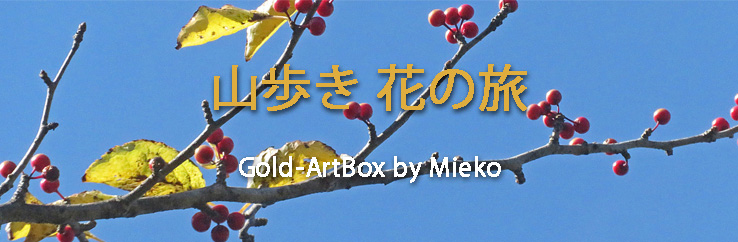606
実りがいっぱい地附山 733m(長野県)
2025年10月30日(木)
また行ってきた、地附山。今朝は夫が公園の駐車場まで送ってくれた。少し遅い時間の出発にしたのはやはり日中に歩きたいと思ったからだが、公園の駐車場には車が多い。
頻繁に登っているから、新しいことはないかもしれないと思いながら、ちょっと違うコースを歩いてみる。公園の中を大きく回っていく道は、旧バードラインが残っているところ、鳥の声が賑やかだ。アカゲラが2羽、話をするように太い木に向かい合って止まっている。




公園を出て、ハイキングコースを登っていく。今日は久しぶりに一人で六号古墳の方まで行ってみる。先日夫と二人で歩いたが、一人で歩くのは久しぶりだ。このコースには粘菌が多いので、私と夫はこっそり「粘菌通り」と呼んでいる。あ、いやもう一人いた。イケさんと3人のこっそりだった。イケさんが見えない世界へ旅立ってからもう1年半が経ってしまったんだなぁと、しみじみ思う。
雨は降ったけれど、あまり粘菌は発生していないようだ。先日見つけた赤いヌカホコリが胞子を飛ばして茶色く変化している。ヌカホコリはないけれど、あちらこちらにマメホコリが顔を出している。まだオレンジ色の新しいものが多い。これからはマメホコリの季節なのだろうか。




粘菌の写真を撮ったり、日の光を受けて赤く輝くガマズミたちの実を撮ったりしながら歩いていく。コバノガマズミはちょっと遅れて赤くなったが、今はどちらも真っ赤に熟れている。ウラジロノキも、アズキナシの木も教えてくれたのはイケさんだった。それぞれの実りをもう一度見ながらゆっくり前方後円墳への道に進む。


久しぶりに晴れたからか、赤トンボがたくさん舞っている。




途中サルトリイバラの実を撮っていたら、一人の男性が「この実は何の実でしょうか」と話しかけてきた。あまり真っ赤に実っていたのでちょっともらってきたと、見せてくれたのはウメモドキのようだ。赤い実がたくさんついている枝には小さな葉もまだしっかり残っている。アオハダの実と大きさは似ているが独特の枝のゴツゴツがない。それにアオハダはすでにかなり実を落としているし、葉もないだろう。「アズキナシではないですか」と男性。アズキナシもウラジロノキも、もっと柄が長いので違うと話し、見られる場所を伝える。男性としばらく話してから、私は山頂へ向かった。


久しぶりに飯縄山と黒姫山、妙高山が綺麗に見える。誰もいない山頂でぼんやり山を眺めていたが、ぽちぽちと登山者がやってきたのを潮に降ることにする。その前に山頂近くのアオハダを見にいく。やっぱり、もう葉はほとんどなく、小さな枝のゴツゴツは遠くからでもよくわかる。


さぁまっすぐ帰ろうと、どんどん降りていく。パワーポイントのところに誰かいる。登りで会った男性だ。挨拶をして歩き始める。この辺にアケビがあった、とか、キノコ採りの男女に会ったとかポツリポツリ話しながら歩調が合って、公園まで一緒に歩いた。
男性は仲間と行った鬼無里の方のキノコ採りの話をしてくれた。たくさん採れたので冷凍したそうだ。地附山にはどんなキノコがあるか、私は怖いのであまり採らないと言うと、ジゴボウやムキタケなら大丈夫と言う。ムキタケはツキヨタケと間違えて中毒になることを聞くから怖いと話すと、その違いを教えてくれた。そして、ここ地附山ではツキヨタケを見たことは一度もないと言う。

彼は地附山の麓に住んでいて、子供の頃からここで遊んでいたのだそうだ。しかも、この山の一部の地所は彼の土地だって、びっくり。
「それでは、そこの木や草を採ってもいいかしら」と冗談を言うと、「いっぱい採っていいよ」と笑う。
公園まで降りると、よく会う山男のスーさんがいた。私と一緒に歩いてきた男性はスーさんと近所だそうで、また話が弾む。しばらく話してから、大急ぎで家に向かう。


途中、スーさんと男性の車を見送って善光寺雲上殿まで降りてきたところで、小柄な女性に呼び止められた。この女性は塩尻の方の山岳会の人で、11月に地附山大峰山の山行を計画しているそうで、そのリーダーをするので下見に来たそうだ。地図と山行計画を見ながら地附山の様子を話して別れた。


山にはさまざまな実がいっぱいで、野生動物の食糧になるのだろうか。だが私がつい目を止めるのは綺麗な色の木の実などばかりで、ドングリなどの地味な落果にはあまり目がいかない。これこそが彼らの食糧なのだと思うけれど。


様々な実りの中に、もう花芽が大きなツノハシバミを見つけてなんだか、嬉しくなった。