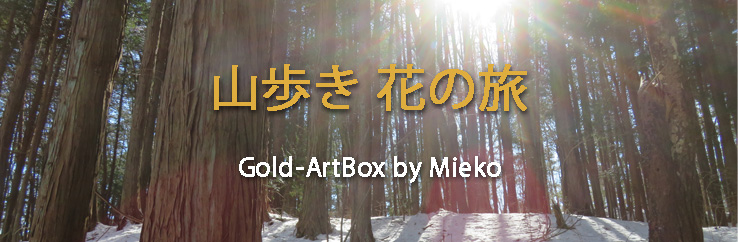537
木漏れ日の中を歩く茶臼山 730m(長野県)
2025年2月21日(金)

ポカポカと温かい陽だまりで木のベンチに座って煎餅を齧る。目の下には川中島の町と新幹線の高架が見える。その向こうには菅平方面の山がちょっと霞んで続いている。頭の上では松ぼっくりをつつく小鳥の声が賑やかだ。ここは茶臼山自然植物園の入り口。冬季閉鎖中で、車は入れないが、歩く人には開かれている広々とした空間が気持ち良い。
寒気が強いのでいつまでも気温はマイナスだが、青空と太陽のコンビネーションが気持ちも空気も暖めてくれる。まだまだ地面に残る雪は多いので、花は期待できないが、少し南に行けば何か発見できるかもしれない、そして青空が綺麗な日はアルプスの展望も期待できるだろうと、出かけてきた。


恐竜公園の入り口に車を停め、整備された自然探索路をゆっくり登っていく。周辺にはほのかに怪しい香りが漂っている。朝日を受けて光る霜とは不似合いな香りだ。気がつくと足元一面に銀杏の実が散り敷いている。匂いの素はこれだ。自然の香りとは言ってもあまり嬉しくない匂いだから早々に先へ進む。


散策路の脇には桜の古木があるが、幹に黄色いスポンジのようなものが張り付いている。時々古い木の幹に見かけることがあるが、大きなものは得体が知れなくてちょっと気味が悪い。さわるとスポンジのようには凹まないが、軽そうだ。ベッコウタケの幼菌に似ているが、はっきり断定はできない。
少し登ると不動島の看板が見える。地すべり地帯の茶臼山一体にあってここは滑らなかったそうだ。たくさんの小鳥の声を聞きながら長野盆地を見下ろす。遠く菅平方面の山並みが見える。真ん中に走る新幹線の高架を見ながら「来るまで待つ?」「いや、今はいいよ」。

少し登って植物園に入ると展望台がある。いつもここから新幹線が来るのを眺めていたが、煎餅を齧りながら小休止している間、新幹線はやってこなかった。


気持ち良い日の光を浴びながら、植物園の中を登って茶臼山の登山道に入る。日があたるのか、雪はかなり溶けている。植物園の中には大きな木があるが、葉を落としているとなんの木か分からない。時々分かるのを見つけると嬉しくなる。
毛皮を着たようなコブシの冬芽、今にも膨らんで開きそうなシャクナゲの花芽などは分かりやすいので目を惹かれる。スイカズラの丸まった葉も木の枝に絡まって健気に冬を越している。山の斜面には枯れ草の中にヤブランの茂みやシュンランの葉が目立つ。そしてポツポツと倒れながら濃い緑を保っている一枚葉はサイハイランだろうか。「サイハイランが咲く季節に来たことがないね」「今年は来てみなくちゃ」。




急な斜面を登ると、その上はまだ白い世界だった。雪が溶けた落ち葉の道に木の影が伸び、朝日を受け損ねた影の部分にはまだ霜が白く残っている。もう少し日が高くなれば消えてしまう一瞬の芸術だ。
白くなった森の中の道をまず茶臼山山頂に向かう。道の両側には折り重なった倒木が痛々しい。里山が私たちの生活と密接な関わりを持たなくなって久しい、寂しい景観だ。山頂への道は杉や檜の針葉樹林、ほの暗い森の中を大きく巻いて緩やかに登る。針葉樹の森の中へ踏み込むと梢から差し込む光が踊っている。明るい太陽の光を受けて木々の梢が輝いている。こんなとき、つい呟いてしまう「お日様は偉大だ」。



私たちは木漏れ日の煌めく光の中をゆっくり山頂に向かう。木の間越しの光は私たちが動くたびにチラチラ、キラキラと姿を変える。近づく山頂は白く光っているようだ。いつもは暗い森の中の山頂が今日は太陽の光を受けてキラキラしている。



いつになく明るい山頂だけれど、見晴らしはない。アルプス展望台へ行ってみよう。東の空にかかっていた雲が広がってきたようだ。雪の中を少し歩くとアルプス展望台。残念、西の空にも雲がかかっていた。目の前に広がっているのは麓の集落。その向こうにアルプスの山麓。雲の動きとともに時々裾野を見せているのは五竜遠見尾根、八方尾根などの下部、八方尾根は真っ白だ。今年は雪が多く4、5メートルの積雪と聞く。スキー場は嬉しいかも知れないが、生活はきついだろうと思いながら眺めている。 しばらく眺めていたが、雲は上がらないので今日は諦めて降りよう。日向へ行っておやつを食べようかと話しながら降りるが、広がってきた雲が太陽を隠すと一気に寒くなる。
途中で見つけた粘菌は春を待って固まっているようだし、一個だけ見つけたフキノトウは気が早く顔を出して霜にやられてしまったようで茶色く固まっている。暖かくなったり冷え込んだりを繰り返しながら、少しずつ春が近づいているのかも知れない。一個だけのフキノトウは夜のお味噌汁でいただいた。なんともいえぬ香りに春の到来が近いことを感じた。