42
花咲き乱れる八石山 513.8m(新潟県)
2018年4月19日(水)
長岡市に住む弟から八石(はちこく)山のパンフレットをもらったのは、もう何年か前のことだ。花の多い山だという。行ってみたいが、長野からでは距離がある。
里山の中でも標高の低い山に1日がかりで行くのをためらうのは、なぜだろうか。同じ時間をかけて行くのならもっと高い山に!などという欲張り根性の現れか・・・。どこかにそんなさもしい根性も確かにあるようだ。けれど、数字で表せる順番だけに意味があるわけではない。そこに立って嬉しいと感じればいいではないかと思うのもまた確かだ。弟の便りに『もうシラネアオイが開き始めた』とある、行ってこよう!




朝7時少し前に家を出る。裏山から牟礼を越えて上信越道信濃町ICまで霧の濃い道を走る。昨日は雨、大地の水分が一気に浮遊してきた感じだ。高速を走りだすとすぐ新潟県に入る。さっきまでの霧がうそのように消え、快晴の青空。まだ雪景色の妙高山、火打山が眩しいほどにそびえている。

日本海を左に見ながら走り、右に米山を見てしばらく行く。米山はまだ雪を乗せているが、麓の山は春の花が楽しそうだ。日本海と分かれ、柏崎ICで降りる。ここからは弟からもらったパンフレットを見ながら進む。国道252号から291号に、そして右に折れていく。前方には、ぼこぼこと盛り上がった山容の八石山が見えている。
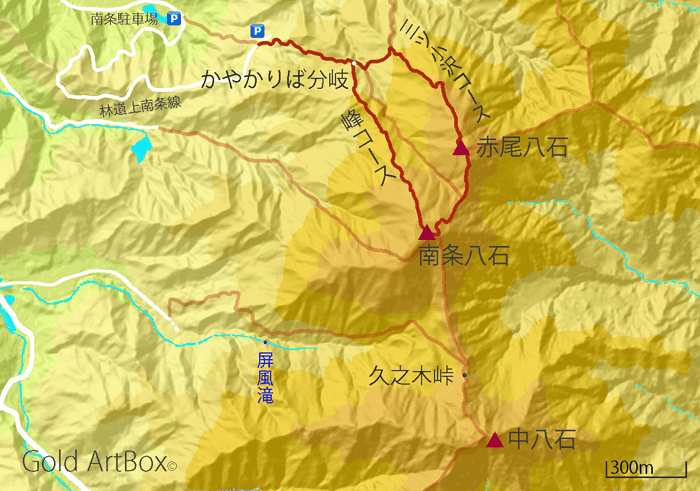
下の駐車場を通り越し、地図に頼って上の駐車場まで進む。この道はなかなかの山道ですれ違いも困難だったから、下の駐車場に停めて登れば良かったと思ったのだったが、それは後の祭りと言うもの。ただ、上の駐車場に続く道の脇の崖には楽しみにしていたオオバキスミレやイワカガミが群落になって咲いていたので、助手席の私は大喜び。


上の駐車場に着いて、靴を履き替えるのももどかしく、花の中に入っていく。トキワイカリソウが純白の花をぶら下げている。エンレイソウ、ニリンソウ、アズマイチゲも、オオバキスミレも・・・。歩くより写真を撮る時間の方が長い・・・かもしれない。歓喜。振り返れば笑い始めた里山の向こうに日本海の紺。青空に浮かぶ、白い雪で彩った米山。なんて素敵な今日の時間だろう。




歩いても、歩いてもカタクリ、トキワイカリソウ、オオバキスミレの群落が続いている。




下の駐車場、上の駐車場、平日だけれど車は多い。この、低いけれど豊かな山の恵に触れたい人が沢山いるのだろう。地元の人が『はちこくさん』と呼んで大切にしていることがうなずける。
私たちは弟の情報を便りに三ツ小沢コースに進む。下に水音を響かせていた赤尾川の源流に近いと思われる沢を渡り、急登をぐんぐん進む。今日の目的は自然の中に咲くシラネアオイに会うこと。でも、なかなか現れない。スミレサイシン、ナガハシスミレが沢山咲いている。チゴユリもアマドコロも花を開き始めている。











「本当にこのコース?」と、首を傾げかけた時、見つけた!大輪のシラネアオイ。柔らかそうな薄紫の花びら(本当は萼)を心持ちうつむきかげんに開いている。いくつかの株にそれぞれ数輪の花が揺れていた。
しばしシラネアオイと向き合ってその色をめで、柔らかな花の姿に息を呑み、たっぷり楽しんでから・・・私たちはまた登り始めた。駐車場には車が何台も停まっていたが、嬉しいことに人に会わず、静かな山道だ。夫は「さぁ、帰ろうか」と、ジョークを飛ばす。そう、今日の目的はシラネアオイに会うことが一番、だからもう満足。
でも、じつはもう一つ目的があった。隠れた目的、それはコシノカンアオイに会うこと。私はなぜか地味なカンアオイ属に心引かれる。カンアオイ属は、生育地を広げるのにとても時間がかかるのだそうで、それぞれの地で独特の進化をしているそうだ。コシノカンアオイは中でも大型なもの、絶滅が心配されているという。以前角田山に登った時に初めて出会った。今日は再開を期待している。

八石山のパンフレットには赤尾八石(474m)と、南条八石(513.8m)のピークが載っている。私たちが登っている三ツ小沢コースは赤尾八石山を越えて南条八石山に達するもの。稜線の登山道脇にはカンアオイの葉が沢山見られる。私は葉の脇の落ち葉をそっとどかしては葉の根元をのぞくが、なかなか花を見つけられない。先を歩く夫は退屈そうに残雪の写真を撮って時間つぶしをしている。
そして、やっと見つけた。コシノカンアオイの大きな花。大きいと言ってもカンアオイ属の中では、の話。大きな手の人の親指くらいの大きさ、地味な赤茶色の花がころりと地面に転がっている。私にはそれが面白い。


楽しみにしていた花に会えたので、心が弾んでいる。稜線の脇には残雪が多い。標高が低くても雪が多かったのだろう。赤尾八石の山頂には展望台があり、越後三山が目の前に見える。右奥には双耳峰の巻機山だろうか、左には幾重にも白い山が霞んで見えている。北の朝日連峰。飯豊連峰まで見えるのだろうか。


足元にはカタクリのピンク、目の高さにはユキツバキの深紅、どこまでも続く花の色を楽しみながら南条八石山を目指す。残雪の上を歩いて到着。
山頂は緩やかな広がりを見せて、日差しに包まれ、のどかだ。何人かの登山者が見晴らしを楽しんでいる。赤尾八石の登山道ではほとんど人に会わなかったが、ここ南条八石では登山者があちこちに腰を下ろして一息入れている。私たちも、山頂のベンチに座っておやつを食べた。



「あそこに見える川岸の家から来ました」と言う男性が「すぐ奥に見えるのが中八石山、その右が黒姫山。米山と合わせて刈羽三山と言います」と、指差して説明してくれる。私たちが長野から来たと言うとビックリする。長野県と言えば日本アルプス、山が多い県として知られているから・・・。
のどかな日差しを喜ぶように黄色いアゲハに似たチョウが舞っている。アゲハにしては小さい。あとで夫が調べた、ヒメギフチョウ。カタクリなどの花の蜜を吸うそうだ。山頂には鮮やかなラインのキアゲハも優雅に舞っている。



風が無く、のどかな暖かい日差しに包まれてしばらくのんびりしたあと、今度は峰コースを下る。カタクリはもちろん、ショウジョウバカマが森の中に点々と咲く。八石山のショウジョウバカマは白に近い色が多い。長野の里山で見る花はピンクが濃いものが多い。隣にはイワカガミがポツポツと花を開き始めていた。








ていねいに木を伏せて作られた急な階段の道を、再び花々に包まれながら降りる。春の花を『妖精』とは誰が名付けたか・・・。私たちは妖精達に別れを告げながら、ゆっくり、ゆっくり降りた。
