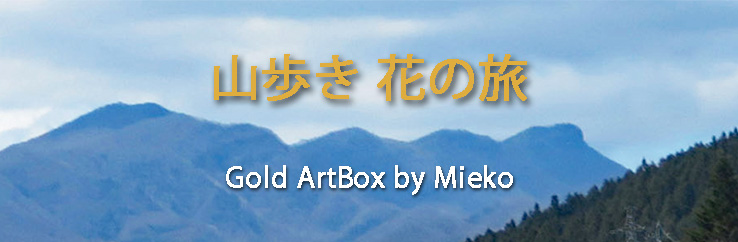101
二度のチャレンジ 鼻曲山 1654m(群馬県、長野県)
2000年3月5日(日)2020.4 記

群馬から上信越自動車道を長野に向かって帰るとき、あの独特の鉤鼻のような形の山容が目の前に見える。
鼻曲山に私たちは二度挑戦した。最初は10月に群馬の霧積温泉から歩き始めたが、標高1500メートル地点で、夫の体調が悪くなり諦めた。


「あの時はどうなったんだっけ?」「急に体調不良になったんだよ。水分不足だったんじゃないかな」。汗っかきの夫が、その後いくつかの山で経験した軽い脱水症状、最近は事前に防げるようになったけれど、鼻曲山に登った時はまだ山歩きの経験も少なかった。写真を見ると引き返す直前の休憩では汗をかいたシャツを木に干してある。水分を取り、塩分のあるおやつを食べて下りてきたら元気になった。転んでもただでは起きぬと、登山口近くの信越本線の廃線跡を訪ね、まだ電車が走ってきそうな線路を歩いてみた。


再び鼻曲山に挑戦したのは2000年3月、まだ雪が残る季節だった。日曜日だけれど、いつもと同じ6時半の電車に乗って出発。東京駅から新幹線で軽井沢に向かう。車ではなく電車で山に向かうことは少ないのでワクワクしていた。軽井沢からはタクシーで登山口の長日向まで入る。歩き始めたのは10時20分と、記録に書いてある。

長日向からは直登コースで山頂へ。登り始めてしばらくすると、後方に浅間山が大きく見えていた。真っ白に雪を乗せている。佐久、小諸方面から見る姿より鋭角に尖っていて美しい。いくつもの外輪山は浅間山の向こうに隠れているので、富士のような独立峰に見える。
思ったより雪が多く、道が所々消えていたが、ひたすら登れば山頂に到着するだろうと呑気に歩いて行った。真っ白な浅間山の上に青空が広がっているから、のんびり気分でいられたのだろう。

私たちは雪の残る道が好きだ。子ども時代を雪深い土地で過ごしたこともその理由かもしれない。もちろん、雪崩の起こりそうな一面に積もった斜面の雪、急な崖の凍りつくような雪、体が潜ってしまうようなラッセルを必要とする雪、張り出した雪庇を踏み抜いてしまう危険をはらむ痩せ尾根の雪などはごめんだ。いわゆる冬山登山の技術はない。けれど、暖かくなってきた季節の、残雪の道は気持ちよく歩けるものだ。夏になれば藪に覆われる道も、歩きやすい明るい道になっている。
しかしもちろん、残雪時の危険もある。ガスが濃くなってくると、どこも似たような景色の中で道がわからなくなる。長い雪渓歩きでは転倒や足を滑らせてしまう危険もある。

つまり、どんな季節でも楽しみと危険はある。気を引き締めて歩くなどということは、日常生活ではなかなか経験できないが、それを教えてくれる山はありがたいということか。
登るほどに道は険しくなり、周りの木々も密生している。山頂に到着したのは12時15分。日向の枯れ草の上に腰を下ろしてお昼にしよう。
ゆっくり食べながら、誰もいない静かな山頂を楽しむ。


そろそろ1時、十分山頂を楽しんだので帰ろうか。地図を広げながら、お天気が良いので稜線を辿って旧碓氷峠まで歩こうと話した。もっと雪が多いようなら来た道を引き返そうと話していたのだけれど・・・。


はじめは良かった。留夫山に差し掛かる頃には雪は深くなり、登山道は全く踏み跡もなく雪原の中に隠れて思わぬ雪山歩きとなってしまった。途中で突き当たった林道を歩いて山頂は巻いていくことにしたが、その林道らしき道がなくなってしまった。深い雪の中を地図と太陽の位置で確認しながら留夫山の西を巻く。雲が出てきて、太陽も薄い雲の向こうになっているが、それでもその位置がわかってありがたい。


深い雪を踏みながら南斜面に回り込むと、雪が少なくなり、登山道らしきところにたどり着いた。ここからは気持ち良い残雪の稜線歩きとなり、ホッとする。
二人だけの稜線歩きを楽しみながら、最後のピーク、一ノ字山1336mを踏み、下りにかかる。


旧碓氷峠には神社の中央が2県にまたがった、珍しい神社がある。熊野皇大神社、境内には長野県、群馬県の境を表す標識がある。この時は知らなかったけれど、ここは熊野総本の熊野三山、山形県の熊野神社と並んで、日本三熊野の一つなのだそう。
旧中山道の碓氷峠、標高1200mは難所だった。ここで力餅を食べてまた頑張って歩き出しただろう古の旅人に想いを馳せながら、峠の茶屋で碓氷蕎麦と力餅を食べる。電車の旅の良さは、ここでビールを楽しめること、かな。

雪の山道を頑張って降りてきたご褒美に再びタクシーを奮発。峠の茶屋で3、40分ゆっくり休み、タクシーに乗ったのは4時を少し回っていた。
軽井沢駅から乗った長野新幹線「あさま」は、都会の賑わいを移したかのように混雑していた。